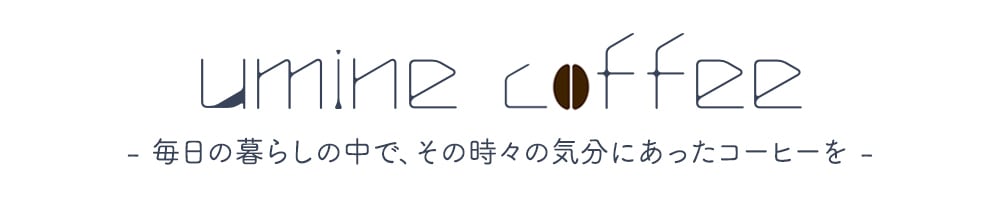- 毎日の暮らしの中で、その時々の気分にあったコーヒーを -
焙煎豆の選び方
焙煎度による味の違いについて
コーヒー豆は、焙煎の度合いで豆の持つ味や香ばしさ、風味、コク、酸味と苦味のバランスが変わります。
中煎り
ウミネコーヒーでは、1ハゼ終わりから2ハゼ開始前の間、ミディアムローストからハイローストにあたる焙煎度合いを中煎りと表記しています。
ウミネコーヒーの中煎り焙煎は、コーヒーの風味、苦味や酸味、香りなど、豆本来の味わいを感じやすく、個々の豆の本質が分かりやすい焙煎度で、特に、スペシャルティコーヒーが持つ良質な酸味や華やかな香りを感じやすい焙煎具合になっています。酸味とコクのバランスが良いのも特徴です。
少し粗めに挽いて、高温の湯で少し薄め(豆少なめ)に淹れて飲むと、豆の特徴を感じやすいかと思います。
中深煎り
ウミネコーヒーでは、2ハゼ開始後、ハイローストとシティローストの中間にあたる焙煎度合いを中深煎りと表記しています。
中煎りと比べ、酸味が弱まり、苦味・コクが増して味に深みがあります。苦味のバランスに優れ、さらにコーヒーらしい甘みがあります。
少し細めに挽いて、普段より低めの温度で淹れて飲むと苦味が強くですぎず、まろやかな甘さを楽しめます。
中-中深煎り
ウミネコーヒーでは、上記の焙煎度合いを目安に、2ハゼ開始直後、中煎りと中深煎りの豆が混ざり合った状態の焙煎度合いを中-中深煎りと表記しています。
スペシャルティコーヒーの風味特徴を楽しみたい、けどコクのあるコーヒー感も味わいたい、そんな方にもオススメです。
コーヒー豆の品種について
豆の品種により味の傾向はありますが、生産地ごとの地理的特性や生産処理 (精製) 方法、焙煎具合、飲み手の嗜好などにより感じ方が変わりますので、ウミネコーヒーでは、品種による味の違いについての説明は割愛させていただきます。
ティピカ
歴史上最も古い栽培品種で他の品種の大本とも言える品種。
パチェ
ティピカ種の変異種。
ブルボン
ティピカ同様、アラビカの二大栽培品種のうちの一つ。カトゥーラ、カトゥアイ、ビジャサルチなど、様々な派生品種の基礎とも言える品種。
カトゥーラ
ブラジルのミナスジェライス州で発見された、ブルボン種の自然突然変異によって生まれた品種。
カトゥーラ・チロソ
カトゥーラに非常に似た樹形ながら、生豆の先端が尖ったロングベリーのような形状が特徴
カトゥアイ
ブラジルのカンピーナス農業試験場が開発した、カトゥーラとムンドノーボ(ティピカ種とブルボン種の自然交配種)の交配種。
ビジャサルチ
コスタリカのサルチ村で発見されたブルボンの変異種。
アカイア
ムンドノーボ種(ティピカ種とブルボン種の自然交配種)のうち、大きな果実がなるものだけで交配した品種。
エチオピア原生種
エチオピアはアラビカコーヒーのルーツとされており、自生する品種がとても多く、その品種は数千種類以上とも言われています。 エチオピアでは、品種等の生産管理を行っているところはごく一部で、その土地に自生している野生種のコーヒーを収穫することが伝統的に行われています。
N39(ブルボン種由来) & KP423(ケント種由来)
タンザニアのリャムングコーヒー研究所で開発された伝統的な品種。
*ケント種=インドでサビ病への耐性を強化するために改良された品種
テキシク
エルサルバドル生まれのブルボンの選抜品種。ISIC (エルサルバドル国立コーヒー研究所)が、1970年代後半にコーヒー栽培を確立するための支援を行いました。
アテン(カティモール種)
主にスマトラ島を中心に植えられている品種。アチェ州Aceh Tenggah地区の名前からアテンと名づけられました。
ティムティム(ティモール・ティムール)
ティピカ種とロブスタ種の自然交配種(ほとんどのハイブリッド系品種の先祖)
SL28種
ブルボン種系に属する、ケニアを代表する品種の一つ。
ルイル11
ケニアの首都からほど近いルイルというところにあるコーヒー研究所で、SL-28、SL-34、K7、ルメ・スーダンなど複数の品種を掛け合わせたものに、カティモールと交配させてうまれたハイブリッド品種。
パカマラ
矮性の品種「パーカス」と、大型の品種「マラゴジッペ」を交配して作られた品種です。
マラゴジッペ
ブラジルで発見されたティピカの突然変異種。大きな粒が特徴。
パーカス
エルサルバドルにて発見された、ブルボンの突然変異種。
マラカトゥーラ
マラゴジッペとカトゥーラの交配させてうまれた品種。
パライネマ
サルチモールの系統選抜品種。
生産処理 (精製) 方法による味の違いについて
同じコーヒーチェリーを使っても、生産処理方法を変えると、コーヒーの味は大きく変わります。コーヒーの精製方法は大きく分けて二種類、ナチュラル(水を使わない方法)と、ウォッシュド(水を使う方法)があります。また、現在では精選設備の進歩によりそれぞれにいくつかの違う方法があり、味覚の違いを追求する生産者も多くなっています。
ナチュラル(天日干し)
ブラジル、エチオピア、イエメンでは一般的な方法
コーヒーチェリーの果肉を残してそのまま乾燥させるので、品種や土壌に関わらず、コーヒーに果実味のあるフレーバーが加わりやすいです。また、独特の香りや甘みがあるコーヒーになりやすいです。
ウォッシュド(水洗処理)
多くの国で一般的な方法
手間がかかりますが水洗処理する過程で欠点豆がある程度除去されるので、雑味の少ないクリーンで良質な酸味のコーヒーになりやすいです。
発酵過程を通したものをフリウォッシュド、機械的に除去したものをパルプドアンドデミューシレ―ジド やセミウォッシュド と区別することもあります。
パルプドナチュラル(ハニープロセス)
パルプドナチュラルはコーヒーの実をパルパーという機械にかけ、皮とパルプ質を剥いだのち、そのまま乾燥工程に入るものです。通常のウォッシュドよりも甘味やコクのある豆になる傾向があります。乾燥の過程により、レッドハニーコーヒー、イエローハニーコーヒーなどと名付けられることもあります。
スマトラ式(セミウォッシュド)
インドネシアでよく行われる製法
コーヒーチェリーは収穫後、果肉を除去して、軽く乾燥させます。他の方式では水分量を11~12%にするのに対し、スマトラ式では30~35%で終わらせます。その後、パーチメント(内果皮)を取り除いて生豆にしてから、再度、腐敗の心配がなく保存できる状態になるまで乾かします。
酸味が弱く、コクが強い、独特な風味になりやすいです。
生産地の標高による味の違いについて
味の好みは人それぞれなので一概に味の良し悪しは決まりませんが、一般的に、標高が高いエリアで栽培されたコーヒー豆は、高品質に育ちやすい傾向があります。
標高が高い → 香りが豊かで質の良い酸味になる傾向
標高が低い → 芳ばしくマイルドな風味になる傾向
スペシャルティコーヒーとは
ウミネコーヒーが焙煎/販売する“スペシャルティコーヒー”とは
1. スペシャルティコーヒーならではの魅力ある風味特性を持つこと
2. 生産から精製、流通までの経路が、明確かつ追跡可能であること
3. 自然環境を尊重し、人道的な取り組みによって生産されていること
4. 品質に対する付加価値が支払われて取引されていること
5. 品質が確かであること